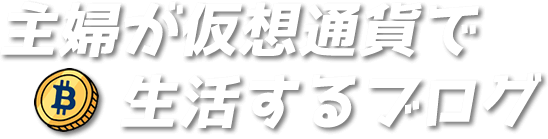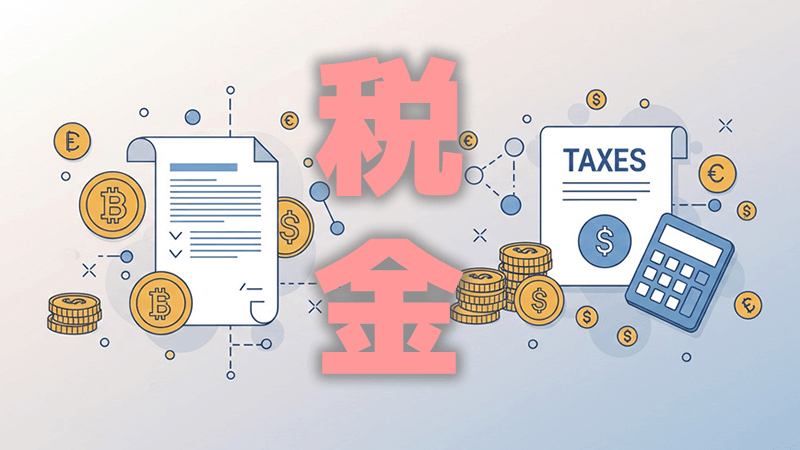近年、暗号資産(仮想通貨)市場は成熟し、個人投資家の利用も拡大しています。これに伴い、税務当局や業界団体による税制改正の動きも活発化しています。
日本では依然として仮想通貨取引の利益は「雑所得」として総合課税の対象となり、最大税率は所得税45%に住民税10%で最大55%となります。
しかし、業界からは株式やFXと同様の【申告分離課税】(一律約20%)や損失の繰越控除の導入など、税制の見直しが求められており、2025年度の改正を期待する声も多いです。
本記事では、最新の情報を踏まえて、暗号資産(仮想通貨)に関する税金の基本知識、課税対象となるタイミング、計算方法の例、そして節税対策などについて初心者にもわかりやすく解説します。
仮想通貨の税金の基本知識
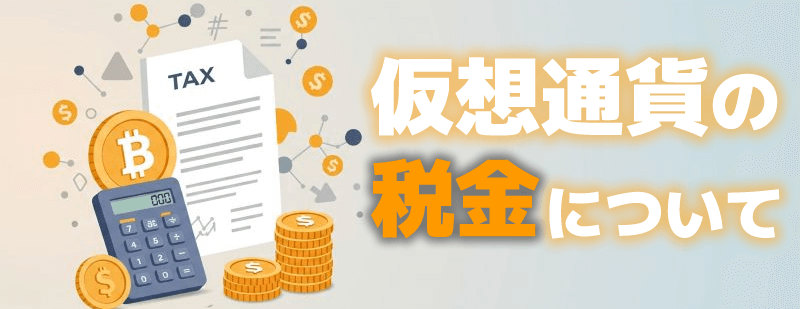
仮想通貨は原則「雑所得」
雑所得は他の所得(本業の給料など)と損益計算が一緒にできないので「雑所得のみ」で損益計算をする必要があり、「雑所得が黒字で、他の所得が赤字でも相殺はできない」という大きな特徴を持っています。※雑所得内では損益計算が可能
非課税の条件
雑所得は「雑所得内」では損益計算ができるので、1年間を通して他の雑所得の利益と通算して年間20万円以下なら課税対象にはなりません。
逆に言うと年間で20万円以上の利益がある場合は課税対象となり確定申告が必要となります。ただし、給与所得者(サラリーマン)ではなく、個人事業主の場合は年間38万円を超える利益があれば確定申告が必要になります。
※給与所得者でも個人事業主でも仮想通貨取引以外に所得がある場合は、それらを合算した合計金額(総合課税)になります。
20万円以下なら所得税は非課税ですが、住民税はかかるので注意が必要です。住民税は役所の管轄になります。
現行制度の不利な点
現行における暗号資産(仮想通貨)税制度の不利な点は以下のようなものがあります。
仮想通貨に税金がかかるタイミング
暗号資産(仮想通貨)の利益が確定する主なタイミングは主に以下の3通りです。これらで利益を得た場合に、課税対象となり税金がかかります。
仮想通貨自体は非課税なので、ただ単に仮想通貨を持っているだけでは課税対象になりません。もちろん含み益がでていても仮想通貨を動かさなければ税金はかかりません。
利益確定となる取引例
- 暗号資産(仮想通貨)で物品を購入した場合
例:10万円で購入したビットコインが30万円に値上がりした状態で、30万円の商品を購入→利益20万円が確定。 - 暗号資産(仮想通貨)を売却した場合
例:10万円で購入し、30万円で売却→利益20万円が課税対象。 - 暗号資産(仮想通貨)同士を交換した場合
例:10万円で購入したビットコインで、30万円分のイーサリアムを購入→利益20万円が確定。ただし、交換後の相場変動により実際の申告時の評価額が変動する場合もある。
取引の年度内で利益・損失を計算する必要があり、年度またぎの場合は申告方法が変わる点に注意。
税金の計算方法と具体例

基本の計算式
暗号資産(仮想通貨)の損益計算を最も簡単な式に表すと「売却価額 – 取得単価 × 売却数量」というシンプルな計算式になります。
売却時の金額 - (取得単価 × 売却数量)= 利益
※取得単価は「移動平均法」または「総平均法」で算出します。
移動平均法と総平均法の違い
暗号資産(仮想通貨)を複数回の取引で異なった価格で取得した場合は、別途「取得価格」を算出しないといけません。この取得単価の算出方法には、「移動平均」と「総平均法」というものがあります。
移動平均法と総平均法の取引例
説明だけでは、分かりにくいと思うので実際の例を出して確認してみましょう。
- 1月10日 200万円で1BTCを購入
- 3月15日 100万円で1BTCを購入
- 8月20日 250万円で1BTCを売却
- 10月5日 150万円で1BTCを売却
- 12月9日 120万円で1BTCを購入
移動平均法の計算方法
取得価格の算出
(①200万円 + ②100万円)÷ 2BTC = 150万円(取得価格)
利益計算
(③250万円 + ④150万円)- (150万円(取得価格) × 2BTC)= 100万円(利益額/課税される金額)
総平均法の計算方法
取得価格の算出
(①200万円 + ②100万円 + ⑤120万円)÷ 3BTC = 140万円(取得価格)
利益計算
(③250万円 + ④150万円)- (140万円(取得価格)× 2BTC)= 120万円(利益額/課税される金額)
税率と計算例
| 利益額 | 所得税率 | 控除額 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | なし | 10% |
| 195万円以上 330万円以下 | 10% | 97,500円 | |
| 330万円以上 695万円以下 | 20% | 427,500円 | |
| 695万円以上 900万円以下 | 23% | 636,000円 | |
| 900万円以上 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | |
| 1,800万円以上 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
- 所得税:300万円 × 10% − 97,500円 = 202,500円
- 住民税:300万円 × 10% = 300,000円
- 合計:202,500円(所得税) + 300,000円(住民税) = 502,500円
また暗号資産(仮想通貨)は「総合課税」となるので、他の所得と合算して税金を計算します。
総合課税として合算される所得は以下の8つあります。
- 利子所得
- 配当所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得

多くの方が給与所得もしくは事業所得をもらっていると思うけど、仮想通貨の税金は、このお給料等と合算して計算しないといけないってことだね
例えば、給与所得が510万円、暗号資産(仮想通貨)の利益が300万円なら合計で810万円の総合課税になり、所得税33%+住民税10%の43%課税されます。
例:(給与所得510万円+仮想通貨の利益300万円) × 43% – 1,536,000円(控除額) = 1,947,000円(課税額)
最新の税制改正の動向と今後の展望
業界団体からの税制改正要望
近年、【日本暗号資産取引業協会(JVCEA)】や【日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)】などから、以下の点について税制改正の要望が提出されています。
国民民主党からの税制改正要望
業界団体からの要望に加えて、国民民主党の玉木雄一郎代表がX上で発信した税制改正要望について紹介します。
玉木代表は、現行の雑所得課税による高い税率(最大55%)に対し、株式やFX取引と同様の申告分離課税(約20%)への転換を強く求めています。具体的には、以下のような趣旨の内容です。
この要望は、暗号資産(仮想通貨)取引の普及とともに投資家の負担軽減を目指す動きの一端として、今後の税制改正に大きな影響を与える可能性があります。

日本の仮想通貨税制は世界一過酷ともいわれてるよ!国内のイノベーションを阻害している要因でもあるから一日でも早い税改正を求めたいね!
今後のスケジュール感
- 業界団体からの要望は2024年後半に提出され、2025年度の税制改正大綱に反映される可能性があります。
- 国会での審議を経て、改正が実施されれば、2025年以降の申告分離課税および損失繰越制度の適用が検討される見込みです。
節税対策と実務上のポイント
①必要経費の計上
「暗号資産(仮想通貨)の利益 – 必要経費 」で出た金額が課税対象となります。
取引手数料、パソコン、通信費など、暗号資産(仮想通貨)取引に直接関連する費用は必要経費として計上できます。経費として認められるかは、税務署からの指摘に対応できる根拠が必要です。
例えば、個人事業主として開業して、仮想通貨の利益をから経費を引くと課税される金額が減り節税できます。※開業届を出さなくても経費の計上は可能
必要経費は税務署から指摘があった場合にしっかりと指摘に対して対応できる根拠が必要です。※顧問税理士がいる場合は必ずご確認ください。
②法人格の取得
これは一般の方からすると少しハードルが高くなりますが、利益が何千万円、もしくは何億円も出ている場合は、法人格を取得してしまうのも一つの手かもしれません。
暗号資産(仮想通貨)で出た利益を会社のものとしてしまえば(それ相応の理由と根拠が必要)大きく節税できる可能性も有ります。ただし、設立時の要件や運用の透明性など、専門家と十分に相談する必要があります。
また最近では税理士さんや司法書士さんに無料で相談できるところもありますので、そんなところを活用してみてるのもおすすめです。
③ふるさと納税の活用
ふるさと納税は自治体に寄附をして、寄附額に応じた所得税・住民税の還付・控除が受けられる制度です。節税よりもお得というイメージの方が近いかもしれません。
詳しくは各地のふるさと納税サイトをチェックしてみてください。
⇒ 楽天ふるさと納税
仮想通貨の税制についてまとめ
確定申告の実務と注意点
まとめ
2025年現在、日本の暗号資産(仮想通貨)取引の利益は依然として「雑所得」として総合課税の対象で、最大税率は55%に達します。
しかし、業界団体からは申告分離課税化(約20%固定)や損失の繰越控除の導入が要望され、今後の税制改正に期待が寄せられています。
また、必要経費の計上や法人化、ふるさと納税などの対策も検討し、正確な確定申告を行うことで、不要な税負担を回避し健全な投資を続けることが重要です。